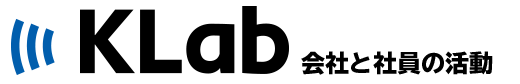【インタビュー連載1】:秒間3,000PVを超えるアクセスを安定して捌く背後に技術者あり~DSAS技術統括責任者が考える技術へのこだわり~
秒間3,000PVを超えるアクセスを安定して捌く実績を持つKLabの『DSAS』。
高い信頼性を備えながらも、低コストでサービスを提供できる舞台裏には
技術者達の存在があります。
DSAS技術統括責任者であり、『[24時間365日] サーバ/インフラを支える技術』の
著者でもある弊社安井に、自身の生い立ちと技術へのこだわりについて聞きました。
コンピュータとの出会いから現在の業務まで、全3回にわたっての連載です。
------------------------------------------------------------------------
プロフィール
安井真伸(やすい まさのぶ)
KLab 研究開発部
インフラストラクチャグループ マネージャ
DSASの開発・運用責任者
---------------------------------------------------------------------------
■ 最近の業務について
-- はじめに、最近の仕事の内容について教えてください。
最近はmixiさんやモバゲーさんのオープン化に伴い、ソーシャルアプリのインフラを提供する"DSAS Hosting for Social"というプロダクトの構築・運用と、コンサルティングをやっています。
-- コンサルティングというのは具体的にいうと?
お客様からこういうアプリを作りたい、っていう企画のベースがあって、それならこういう処理をしないといけないですね、そうするとこういうアーキテクチャで作るといいですよね ということを開発担当の方とお話をしながら提案させてもらったりして決めていくということですね。
■ コンピュータとの出会い
-- 最初にコンピュータと出会ったのはいつ頃ですか?
高校2年ぐらいのとき、友達の家に行ったらファミリーベーシックが転がってたんですよ(笑)
その時「何これ?ちょっと貸して」って言って借りたのが最初です。付属のマニュアルと格闘しながらBASICでプログラムを書いて、どうしてもわからないところは本屋をあさっていろいろ調べながらゲームみたいなものをいくつか作ったりしてました。
それまで「コンピュータ」といえば「自分の手の届かない、なんだかわからないすごい機械」というイメージを持っていたんですが、実際に自分でBASICやアセンブラでプログラムを組むことで、「コンピュータって結局は人間が指示した通りに動くだけの単純な機械じゃん」って感じるようになっていきました。
「結局コンピュータって、指示された通りに数字を出し入れするだけの箱にすぎない」ってことに気づいてからは、パズル感覚でプログラミングを楽しめるようになりました。
■ 学生時代
-- 大学時代はどんなことをしていましたか?
大学は工業大学の電子工学科だったので、電子回路とか無線とかレーザーとかいじってました。
一応、学校の設備としてコンピュータとネットワークはあったけど、それが有効に活用される時代でも環境でもなかったように思います。
-- そのころは自分でどういうものを作っていましたか?
いい加減、ファミリーベーシックはそろそろ卒業しようかなと思って、中古のMSX2を買いました。
ファミリーベーシックではカセットテープにデータを保存してましたが、MSX2にはフロッピーディスクドライブというめちゃくちゃ画期的なデバイスが付いていて。「おおぉ、これ、すげえ!巻き戻さなくていいんだ!」って、やたらとハイテンションになったのを覚えてます。
それで、どんな仕組みになっているのかがとても気になったので、本屋をあさってフロッピーディスクの原理や、データを記録する構造とかをひたすら調べました。その当時はディスクの内容を直接参照したり書き換えたりするツールがなかった(存在すら知らなかった)ので、アセンブラでディスクエディタみたいなものを作って、実際のデータがどうなっているのかを確認していました。
そして、「ああ、こうやってファイルが保存されるんだな」というのを自分の目で確認したり、ディスクのデータを直接書き換えるとファイルの内容も書き換わっていること(当たり前だけど!)に感動したりしてましたね。
このブログについて
KLabの社内や社員の様子、サービスについての情報を発信します。
おすすめ
合わせて読みたい
このブログについて
KLabの社内や社員の様子、サービスについての情報を発信します。